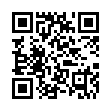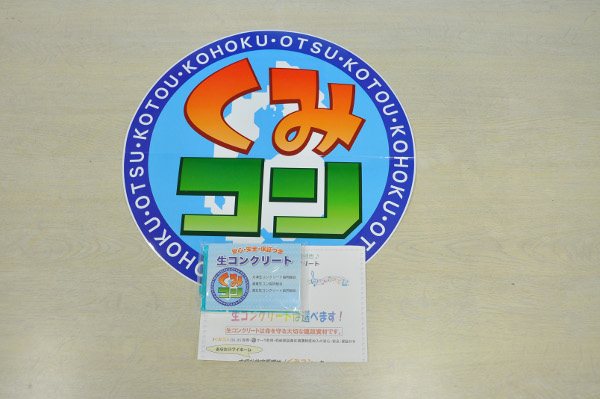一覧へ戻る※資源・環境・リサイクルに対する取り組み(平成10年度調査)
廃材の炭化技術により資源の有効利用に貢献
異業種交流の研究活動で、炭化装置の研究に関心を持つ企業が、木質系建築廃材と間伐材の活用策について提唱し、賛同した有志が融合化開発で廃材の炭化装置を開発した
1.事業の背景
彦根商工会議所の主催する異業種交流の研究活動の過程で、産業廃棄物問題が議題になり、木質系建築廃材と間伐材を炭化物にすることで、有効利用の道が開けるとの提唱に賛同した会員4名で融合化組合を設立した。建設廃材は産業廃棄物の首位の量を占める。また間伐材は市町村が焼却処理しており、処理コストが負担になっている。これらの問題解決と環境改善に役立てるねらいが込められている。
2.事業活動の概要
平成6~8年にわたる融合化開発事業であり、開発テーマの提唱者はかねてから炭化技術に関心を持ち、籾殻炭化装置の開発を行っていた。産業廃棄物問題が深刻になるに従い、自社技術で貢献する可能性を検討していた。その考えが異業種交流の研究で認められ、賛同者4名で融合化組合を設立した。組合の構成員としては、籾殻炭メーカー、木工機械メーカー、制御装置メーカー及び卸業の4社で、開発目的に最適の組み合わせになった。融合化組合の開発テーマは木質廃棄物の炭化装置の開発である。三重大学から基礎理論を学び、炭化物等の物性値の測定について支援を受けた。また継続的な木質系廃棄物の供給の確保が、実験継続に必要となり、県中小企業団体中央会の仲介で協業組合シガウッドとの連携が図られ、チップの安定供給を受けることになった。これらの多角的な連携の結果、炭化装置が完成した。
3.成果
開発された炭化装置は、組合員がそれぞれに設備として販売する方針をとっている。炭化装置で生産された炭化物は、脱臭剤、緑化用土壌改良剤、住宅の床下に敷く湿度管理用等である。これ以外にも用途は多方面にわたる可能性があり、その用途を研究することで装置の販路が開けるとの観点から、目下、販売活動と用途開発を平行して取り組んでいる。
共同事業の新展開-新規事業の実施(平成30年度調査)
高品質の滋賀羽二重糯プリン「湖(うみ)の餅~tae~」登場
組合青年部を中心に試作開発に取り組むとともにデザイン事務所と連携したこと、製造を組合員1社にして品質等の安定を図ったことが新商品開発実現の要因となっている。
1.背景と目的
滋賀県では代表的な菓子土産がないことが問題点として認識され、また当組合では共同購買事業のうるち米の手数料収入減少という問題があり、新たな収益源を開拓する必要があるという課題を認識していた。そこで、新たな組合事業として、滋賀県が誇る高品質の「滋賀羽二重糯」に焦点を当て、新商品開発に取り組んだ。
2.事取組みの手法と内容
①推進方法
商品開発への取り組みの流れは、(1)試作品開発から商品化段階、(2)販売開始から事業拡大の2つに分けられる。
(1)試作開発から商品化段階
試作開発~商品化においては、組合理事会の承認の下で組合青年部と一部組合員で開発プロジェクトを立ち上げて商品試作に取り組んだ。また、パッケージデザインやコンセプト構築に関しては、デザイン事務所と契約しプロジェクトを推進し、滋賀羽二重糯プリン「湖の餅~tae~」を商品化した。
(2)販売開始から事業拡大
商品を発売し、組合員店舗での販売の段階で、理事長及び副理事長が中心となって事業推進組織を立ち上げ、集中的に同一品質で製造~供給するための組織体制を構築した。その体制とは、特定の組合員にて集中して製造し、販売に参加している組合員(15店舗)に商品を供給するものである。また、商品の改善や、今後の商品開発における検討の場として「販売会議」を設置し、定期的に実施している。
②今後の事業課題と展望
今後の課題としては、「販売店の拡大」「知名度向上/ブランディング」「商品開発(ラインナップの拡張)」「推進体制の進化」の4つとなっており、平成30年度は、イベント等を通じた知名度向上への取組みを進めるとともに、「taeシリーズ(※)」としてのラインナップ化に向けた商品開発を行っている。
3.成果とその要因(目標達成状況や今後の期待成果を含む、成果要因・奏功エピソード)
組合運営に危機感をもつ組合執行部及び青年部が精力的に取り組み、デザイン事務所の協力を得てパッケージデザインなどに商品としての魅力を付加できたことが新商品開発の大きな要因となっている。平成29年には190万円を超える売上となっており、平成30年度には4種類の新商品を開発し、「taeシリーズ(※)」として平成31年3月から販売をスタートさせている。 ※「taeシリーズ」詳細につきましては、4月号に掲載予定です。

開発された滋賀羽二重糯プリン「湖の餅~tae~」

平成30年度には4種類の新商品を開発
滋賀県産小麦使用の「近江ソフトめん」の開発と拡販
加工食品で新たなブランドを立上げ一定の支持を得ることは簡単ではない。本事業では、もともと学校給食で馴染みのあるソフトめんをクローズアップしたことが成功のカギとなった。
1.背景と目的
製麺業界は、小麦粉などの原料高や電気料金・物流コストの増加など、経費増加の傾向にあり、さらに競争激化により麺の販売単価下落が続き、収益が悪化している。
そこで、学校給食の人気のメニュー「ソフトめん」を家庭で味わえるように、滋賀県産小麦「ふくさやか」を使用した一般小売り向け商品を開発し、販路拡大 に取り組んだ。
2.取組みの手法と内容
この事業は、大きく「近江ソフトめんの開発」と「情報発信と拡販」の2つに分けられる。
①近江ソフトめんの開発
2017年度の地域特産品等販路開拓支援事業を活用して、「近江ソフトめん」の開発に取り組んだ。
当組合の6組合員は、滋賀県の学校給食事業に給食用麺として「ソフトめん」を供給しているが、委託加工であることからこの製品をそのまま当組合の商品として展開することはできないという制約がある。そこで、組合が独自に小麦の調達から製品化までを行うこととした。
②情報発信と拡販
近江ソフトめんは素材型製品のため、訴求力が弱いという短所がある。
そこで、この製品を使ったメニュー(レシピ)を公募することで、ソフトめんの特質を伝えながら、「近江ソフトめん」を使った「美味しいメニューを提案していく」という手法を採用した。
2018年7月21日に「滋賀県ソフトめんレシピコンテスト2018」を開催し、県民参加型の情報発信を行い、知名度を上げることや、地元信用金庫主催のビジネスマッチング事業への参加などを通じて、販路開拓などに取り組んだ。
本事業は、役員会の元に設置した「ソフトめん展開・実行委員会」が主に活動し、若手理事と事務局で計画的に推進した。
特に本コンテストはメディアにも積極的に取り上げてもらい、NHKや民放のニュースになるなど、インパクトのある成果を得た。
3.成果とその要因(目標達成状況や今後の期待成果を含む、成果要因・奏功エピソード)
本事業で目標としたのは「取扱店の獲得」、「高単価商品でも成立するブランドに育成すること」、「参加組合員の増加」の3つである。
取扱店は当初の18店から32店舗に、参加組合員も当初の6企業から8企業に増え、販売価格も異例の78円/150gを堅持している。
現在では県内のスーパーや農産物直売所、道の駅などで土曜日限定販売が定着している。

コンテストには様々なレシピが応募された

レシピコンテストに参加された皆さん