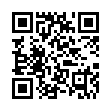行政だけでなく地元の各産業や住民等との連携を図り、町ぐるみでソフト面、ハード
面の両方から「自律」と「持続」のできる、歴史ゆかしいまちづくりを進める。
多賀町は多賀大社の門前町として歴史ある街並みを有し、古くから栄えてきたが、近年交通利用の変化と共に人の流れも大きく変わり、かつての活況を失いつつあった。この危機的状況を打破するために任意団体として活動してきた多賀門前町共栄会は法人化により、施策を活用した積極的な取り組みによる地域活性化を目指して、平成12年に組合を設立した。
活性化の事業は多賀町が策定した「多賀町中心市街地活性化基本計画」と、TMOである多賀町商工会が策定した「中小小売商業高度化事業構想」に基づいて行っている。町や商工会だけでなく住民や交通機関、多賀大社など各種団体と共に形成した多賀町産業連絡会議を発足すると共にワークショップを形成することによって連携事業を検討し、合意形成の流れを作りつつ支援体制を強化している。
ハード面の整備であるファサード整備事業では門前町に相応しい調和の取れた景観づくり、店舗整備を進行中である。また、空き店舗活用事業として門前町の街並みにあった「絵馬館」を3カ所設置、憩いの場として多くの観光客が訪れている。この一方では、ソフト面の整備として、町の風土を守り、創造していく農業との垂直的連携による「そば」の特産品に取り組み、これを個店の業態化の検討と合わせて1商店に1つの名産を生み出す「一店逸品づくり」を行っている。これは「
そば」だけでなく、様々な産品について地元の農業ならびに製造業らと連携し、地産地消の持続あるまちづくりに参画している。
ファサード整備を行った地区においては、売上げ前年比1.5倍を達成するなど、各事業は概ね成功するに至っている。また、関連事業として小学生を対象にした商い体験塾事業を行い、地元住民と社会福祉との接点を強化するといったような目に見えない連携を重ねることで、地域が一体となることが各事業の成功の要因であり、活性化計画の次の段階へとつながる基礎となった。